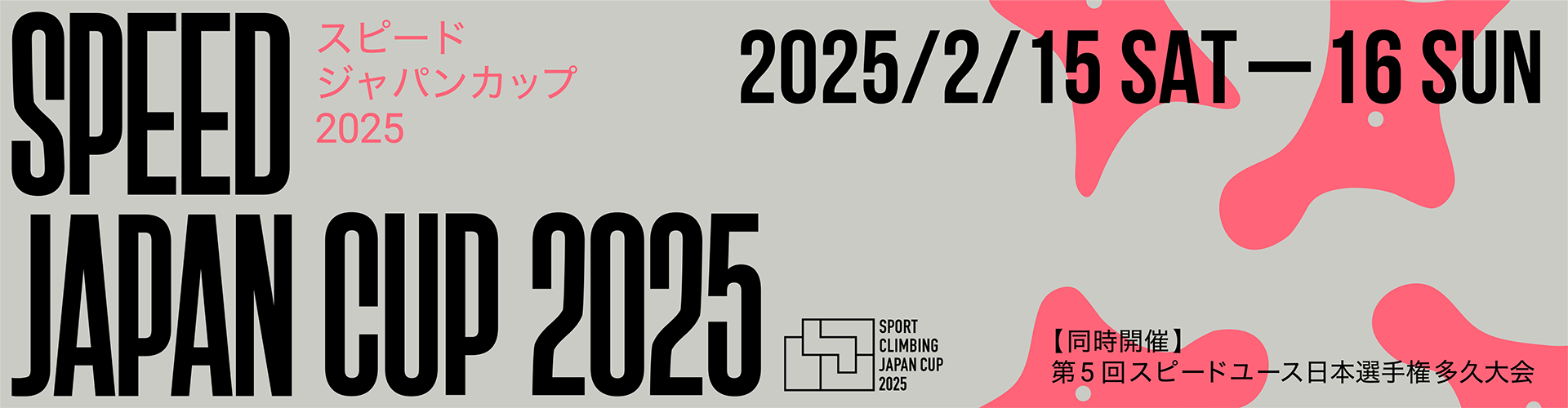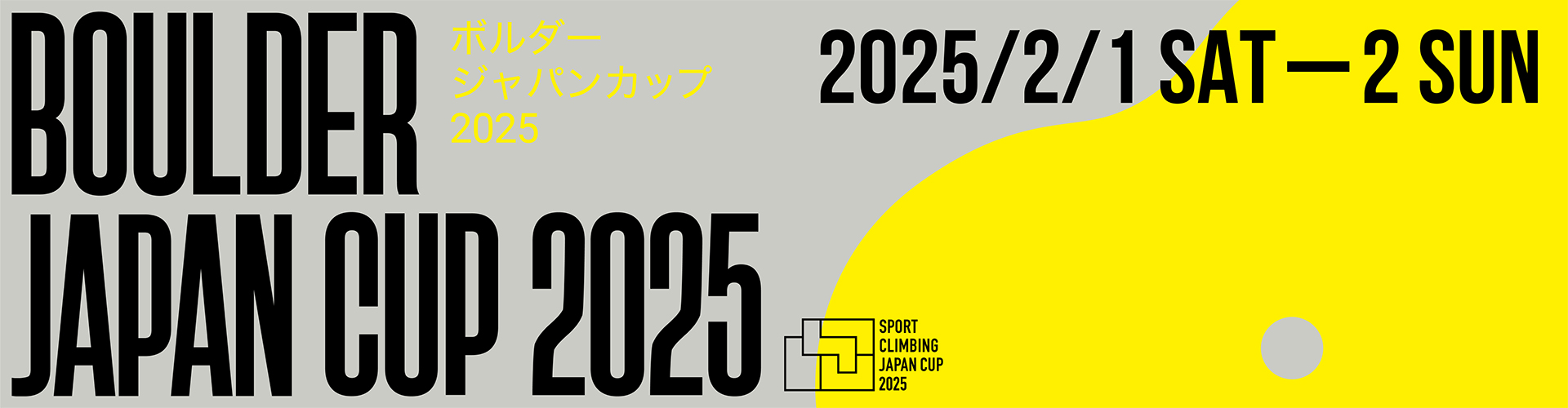『頼れるJMSCA』へ、さらなる進化を目指す

2025年6月22日に開催された理事会で、公益社団法人日本山岳・スポーツクライミング協会(JMSCA)の新会長(代表理事)に町田幸男氏が選任されました。これからのJMSCAを牽引する町田氏に、これまでのあゆみや、新会長としての抱負などについてインタビューしました。
より添い、ささえる、JMSCAをつくる
――町田さんのプロフィールをご紹介ください
私は群馬県太田市の出身です。中学時代は陸上部で1,500mの選手でした。兄が高校時代山岳部に所属していたのですが、山に行きテントを張って自炊して…という姿を見て何て楽しそうなんだろうと感じて、私も高校に進学すると山岳部に入りました。部長になり、いろんなプランを立てては日本各地に足を運んでいました。登山はもちろん、自分でプランを組み立てて行動することや、状況に合わせて安全を守る対応をするといったことに、すごく楽しさを感じましたね。
――そこから約半世紀にわたって山岳に関わってこられたのですね?
そうです。大学でも山岳部で活動し、社会人になってからもずっと関わってきました。18歳からは地元山岳会に所属し、救助隊員としての活動もスタートしました。また、当時の青森国体ではまだ公開種目だった山岳競技に参加し、5位入賞を果たしました。海外登山や救助活動、競技など、さまざまな形で山に向き合ってきました。

――社会人になってからはどのような活動をしていたのですか?
自動車メーカーで、研究開発を手がけるエンジニアとして勤務しました。長期の休みがあれば海外で登山をしましたし、勤務時間を除いては救助隊の活動も継続しました。さまざまな現場を経験し、常に責任を持って対応してきました。
また、文部科学省国立登山研究所講師として招聘され、自衛官や消防士、警察官の方々への救助指導を10年ほど担いました。故人曰く『やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、ほめてやらねば、人は動かじ』を肝に銘じながら、基本的なロープワークから特殊な技術指導まで、幅広い実地研修をしました。自分が登山をする時も“安全”には細心の注意を払っていますが、救助指導の際も遭難者・救助者の両方の安全を守るべくレクチャーしました。
――JMSCAとの関わりはいつ頃からあるのですか?
JMSCAの常任委員に就任したのは2000年のことです。その後、遭難対策委員会委員長のほか、2022年からは登山部部長、翌23年からはスポーツクライミング部部長を務めました。
――クライミング競技にはどのような魅力を感じていますか?
腕力、筋力、といった体力はもちろん重要ですが、それだけでなく知力やセンスも重要になるところが競技としてとてもユニークですし面白いと感じます。困難に直面した際に、選手一人ひとりが違った考え方や方法でクリアしていくのを見るととても感動します。多彩な選手が誕生していますので、JMSCAとしてもいろいろな面からより添い、ささえていきたいと思っています。
具体的な目標を掲げて、着実に進んで行く

――JMSCA新会長に就任して思うこととは?
私は企業人として務めていた期間が長かったので、事業・マーケティングなど多様な目線からの組織づくりをはじめ、より多くの方々にさらに貢献できる協会に進化させていきたいと考えています。
また、日本山岳・スポーツクライミング協会として、普及やサポートへの取り組みを見つめ直すことも重要です。具体的な目標を掲げて、そこに対して何をしていくべきかを全員で明確にしながら、一歩一歩着実に進んで行きたいと思っています。
――「普及やサポート」について具体的に聞かせて下さい
ユースや若手育成の基盤づくりや、競技そのものに触れることができる機会を提供していきます。昨年から体験会を開催し、興味はあるけれどなかなか触れられなかったという方々に、実際に体験していただく機会を増やしています。私自身クライミング競技に携わっていますと人気の拡大を感じる部分もありますが、一般的にはまだまだ知名度の低い競技です。少しでも裾野を広げていくことも使命であると認識しています。
――今後、JMSCAをどのような存在にしていきますか?
『頼れるJMSCA』にしていきます。登山やクライミング競技のオピニオンリーダーとして、協会自体の知名度も高めていく必要があります。各方面から「それならJMSCAに聞いてみよう」「JMSCAにお願いしよう」という存在にして行きたいと思っています。
私自身が“心の余裕”を持ち自分をしっかりと見つめること、そして山で学んだ“おかげさま”の気持ちを大切にして活動していく所存です。登山やクライミング競技をより安全に楽しんでいただけるように、また、さらに人気が高まるように尽力して参りたいと思いますので、皆さまからのご指導・ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。